(1992年 アメリカ)
異端学説を唱えるコロンブスが学会と衝突し、王室を巻き込みながら航海の承認を取り付ける前半部分にはビジネス映画のような面白さがあるのですが、後半にいくにつれて尺不足のために単純な展開が目立つようになり、計ったように面白くなくなりました。前半だけならすべての歴史映画の中でも最上位クラスと言えるほど面白かったんですが。

作品解説
コロンブス航海500周年記念作品
本作が全米公開されたのは1992年10月。コロンブスが西インド諸島に到達した1492年から数えて500周年のアニバーサリーイヤーでした。
そんなアニバーサリー作品だけあってスペイン政府などからの多額の助成金を受けており、製作費は潤沢。復元されたサンタマリア号は本物にしか見えないド迫力であり、金に糸目をつけずに再現された建造物や調度品を眺めているだけでも楽しめます。
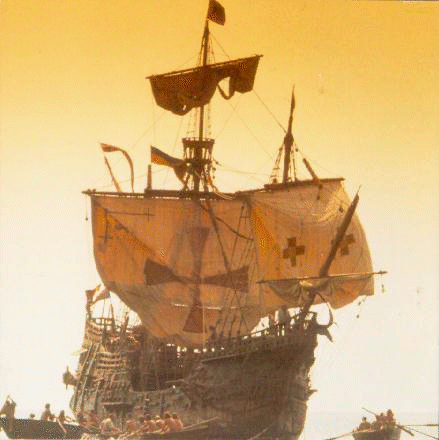
このサンタマリア号のレプリカは撮影後にはスペインに設置され、いまだに年間20万人が訪れる観光名所となっているとのことです。
『コロンブス』(1992年)との関係
なお、本作には競合作がありました。
『スーパーマン』シリーズで知られるメキシコ人プロデューサー アレクサンダー&イリヤ・サルキンド親子が製作した『コロンブス』(1992年)であり、リドリー・スコット監督はこちらからのオファーを先に受けていました。
しかしスコットはこのオファーを断り、その4か月後に本作の監督に就任したものだから、サルキンド親子から盗作で訴えられました。
本作の脚本家ロザリン・ボッシュの執筆開始時期から考えて両作の間にパクったりパクられたりという関係がないことは認められたものの、『コロンブス』というタイトルは使えなくなりました。そのため、アメリカでのタイトルは”1492: Conquest of Paradise”となっています。
なお当該判決が有効なのは北米だけであり、欧州では”クリストファー・コロンブス”のタイトルで公開されました。日本でのタイトルもコロンブスの名を冠しています。
全米公開版と日本公開版の違い
日本国内で流通しているレーザーディスクやDVDに記載された本編ランニングタイム156分に対し、IMDBなどに記載されているランニングタイムは154分。この2分の差って一体何なのかと言うと、主に残酷描写の有無です。
全米公開版ではR指定を避けるため残酷描写がカットされているのですが(PG-13で公開)、日本ではこれがノーカットで上映されました。
90年代にはこうした逆転現象がたまに発生しており、サム・ライミ監督の『クィック&デッド』(1995年)、スタンリー・キューブリック監督の『アイズ・ワイド・シャット』(1999年)も日本公開版の方が北米版よりも長い完全版として公開されました。ともにエロ描写の有無という違いでしたが。
なお、数年前に北米とフランスでリリースされた本作Blu-rayにもこの違いは引き継がれており、北米盤からは残酷描写がカットされたままです。よって輸入盤の購入をご検討の方には完全版が収録されたフランス盤の購入をおすすめします(ただしどちらにも日本語は未収録)。
感想
時代背景について
大航海時代の作品なので、高校世界史の知識で時代背景についておさらいしておきます。
この時代のヨーロッパは停滞期にあり、イスラム勢力との戦争にはよく負けていました。彼らは当時の先進国だったアジアとの貿易を望んでいたものの、地中海の制海権をオスマン帝国に握られていたために貿易ルートを塞がれた状態にありました。
そんな中、イベリア半島では8世紀から続くレコンキスタ(国土回復運動)がようやく実を結びつつあり、その当事国であるスペインとポルトガルでは民族意識の高まりと国王を中心とした強力な中央集権体制が確立されていました。
ヨーロッパで勢いのあったこの2国は国力増強のためアジアとの貿易ルート開拓にも積極的であり、ポルトガルはアフリカ大陸をぐるっと回ってインド洋へ抜けるルートを開拓しようとしていました。これを担ったのはバルトロメウ・ディアスやヴァスコ・ダ・ガマといった航海士達です。
一方スペインはと言うと、アフリカ航路開拓でポルトガルに後れをとったことに焦りを抱えていました。そこに現れたのがイタリア人のクリストファー・コロンブスであり、彼は地球は丸いのだからひたすら西へと航海すればアジアの最東端ジパングに辿り着くはずだという珍説を持ってきました。
ちなみにコロンブスがまず話を持ちかけたのはポルトガルだったのですが、出資を断られたのでライバル・スペインに話を持ち込んだということです。
これが作品の前提部分となります。
ビジネス映画のような前半が面白い
作品はコロンブス(ジェラール・ドパルデュー)の主張が宗教界から激しく拒絶される場面から始まります。
この部分がちょっとわかりづらいのですが、コロンブスも教会も地球球体説を前提としています。争点は次の陸地までどれほど航海せねばならないのかという部分であり、コロンブスはこれを4,800km(実際には約19,000km)と見積もっていました。
しかし当時のキリスト教社会が信じていたアリストテレスやプラトンの宇宙論によると西への航海がその程度で済むはずがなく、宗教家たちは船に積載可能な物資では辿り着けないほど遠いはずだと考えていました。よってコロンブスの考え方は異常だと主張します。
「だったらアリストテレスとプラトンが間違ってるんだよ」と身も蓋もないことを言い出すコロンブス。「なんて罰当たりなことを言うんだ!」と怒る宗教家たち。これが序盤部分です。
革命児らしい歯に衣着せぬ発言のコロンブスと、旧態依然とした学問を守り続ける宗教家たちとの対比は面白く、ベンチャー起業家と古い体質の金融機関のやりとりでも見ているようでした。
科学技術は日進月歩と捉える現在の視点からすると信じられないのですが、中世において学問は古代ギリシャにて完成しており、その教えをひたすら学ぶべきという風潮が支配的でした(『薔薇の名前』などもそんな感じでしたね)。それは東洋においても同じくで、学問は漢代で完成したと考えられており、学者たちは専ら古典の熟読に努めていました。
そこに現れるのが財務長官サンチェス(アーマンド・アサンテ)。
サンチェスは国益の観点からコロンブスの主張に関心を持ち、もしコロンブスの言う通りならばスペインに莫大な富がもたらされるし、失敗したとしても国家財政から見れば些末な損失に過ぎない。投資価値は十分にある案件だから、宗教界はさっさとコロンブスの説を承認せよと圧力をかけます。
また、スペイン女王イサベル1世(シガニー・ウィーバー)からの支持も取り付けます。ただし彼女は国益ではなく、豪胆なコロンブスの性格に惚れ込んでのことでした。
当時の権力である宗教界と対立していたコロンブスが、別の権力者を巻き込んで己のビジョン実現に突き進む様はビジネス映画のようでもあって非常に楽しめました。また宗教界と政界が一枚岩ではなく、静かなパワーゲームを繰り広げているという点にも面白みがあります。
そうして1492年8月、晴れてコロンブスは航海へと出るのですが、船出の直前に「本当のことを言うと船員の引き受け手がなくなるので、航海の距離を少なめに発表しておりました」と懺悔で告白します。
「え?それは今すぐにでも船員達に知らせてあげなきゃいけないやつでは」と焦る神父に対し、「懺悔の内容は絶対に口外しちゃいけないんですよね」と開き直るコロンブス。
結局、コロンブスは事実を伏せたまま航海に出ていくのですが、彼をただの夢想家としてではなく、ずるい面も持った男として描いた点がまた面白く感じました。こういう経営者ってよくいます。本当のことを言うと従業員も投資家も引いてしまうから、都合の良い数字を並べておくしかないだろという。
こうした清濁併せ吞むタイプの偉人って単純な英雄タイプや善人タイプよりも興味深いもので、私は大変に楽しめました。
前半部分は抜群に面白い映画となっています。
中盤以降が駆け足気味
甘い見積もりの下で計画された航海なのだから、当然のことながらうまくいきません。
どこまで行っても陸地が見えてこないものだから船員達は動揺し始め、反乱寸前の雰囲気にまで至ります。丁度良いタイミングで虫や流木など近くに陸地があることの証拠が船に流れ着いて来てコロンブスは何とか求心力を維持し続けるのですが、本当に首の皮一枚のところでした。
この部分をちゃんと描けていれば前半最大の山場になったと思うのですが、船内に漂う疲労感や焦燥感が詳細に描かれていないので、一触即発の緊張感も、ギリギリのところで事なきを得たコロンブスの安堵感も観客には伝わってきません。
その後も西インド諸島の人々との交流や、発見した「楽園」に対するコロンブスの思い入れなどが観客が共感できる形で提示されないので、どうにもイベントが未消化のまま過ぎ去っていくような印象を持ちました。
もし余裕があれば「着想から出航まで」「航海から西インド諸島発見まで」「西インド諸島の統治」の三部作構成で製作するであろうところ、無理矢理に一本の映画に詰め込んでしまったがために尺がまったく足りていません。
単純な勧善懲悪になる終盤のつまらなさ
終盤は植民地経営に躓くコロンブスの姿が描かれます。”Conquest of Paradise”(楽園の征服)という原題から考えてこの部分が作品の本論部分に当たるのだろうと思うのですが、これがどうにもしっくりときませんでした。
ここでのコロンブスはスペインと植民地との間で板挟み状態となります。
そもそもコロンブスの航海は「黄金の国ジパングに至るルート開拓」という大義名分で始まったものなので、スペイン本国は「黄金まだぁ?」という感じです。
しかしコロンブスが到着したのはカリブ海の群島でありジパングではありません。仮に日本に到着したとしても、マルコ・ポーロが吹聴していたような金銀財宝に溢れた国ではなかったわけですが。
そんなわけで本国からの大きな期待に反して、西インド諸島には財産らしきものが何もない。仕方がないので現地人に人海戦術での砂金掘りをやらせてはみたが、大したものは出てこない。
ないものを持って来いと要求される現地人達は疲弊し、一旗揚げようと新天地にやってきた大勢のスペイン人たちは「話が違うじゃねぇか」とイライラを募らせていきます。
そこで破滅の一手となるのがモクシカ(マイケル・ウィンコット)というスペイン貴族で、彼は原住民に対する残虐行為を働いた上、コロンブスに対する反乱を主導します。
ただし終盤の中心人物たるモクシカの扱いがとんでもなく適当で、突然姿を現したかと思ったら、その背景などもまともに描かれない状態で悪だくみを始めるので話全体に説得力がなくなっています。生まれてこの方、ずっと悪人ですみたいな描写だし。
そうして作品全体がこのモクシカにすべての罪を着せるという単純な勧善懲悪の物語となり、それに呼応してコロンブスがつまらない正義の人になってしまうので全然面白くありませんでした。
様々な利害が絡む話として全体を構築してきたのだからこそ、モクシカにもモクシカなりの大義があり、それがコロンブスへの反逆という形で発露したというプロットにすべきだったのに、終盤でそれまでの物語の流れから外れてしまったように感じました。



コメント